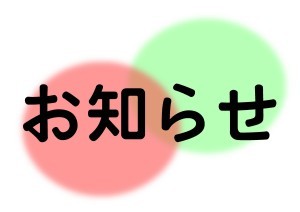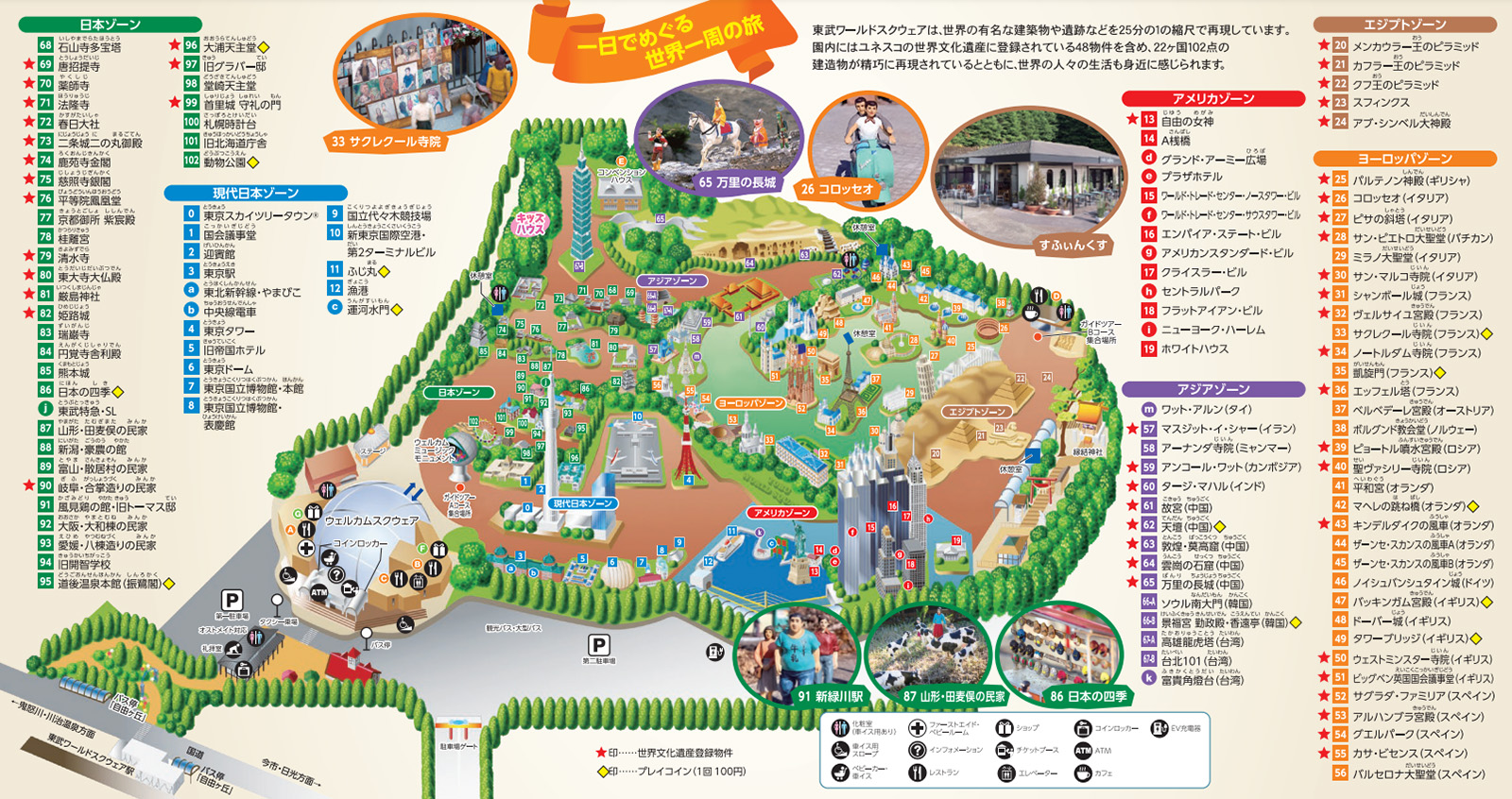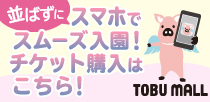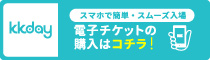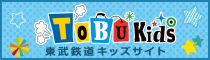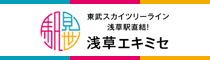News
お知らせ
Guide Map
ガイドマップ


東武ワールドスクウェア公式アカウント